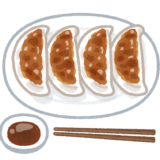「米」という漢字を分解すると「八」「十」「八」が出てきます。このため八十八歳のことを米寿といい、本日八月十八日は「米の日」とされています。
昨年から今年にかけて、店にお米が無い、あっても高くて買えないということが続きました。いわゆる「令和の米騒動」です。これまでも魚や野菜など何らかの水産物や農作物の値段が高騰したり、市場に出回らなかったりということは毎年のニュースに取り上げられていましたが、私個人としては正直なところ、生活をする上で強く意識することはあまりありませんでした。その根底には突き詰めると「食べるものは他にもあるし…」という気持ちがあったと思います。贅沢な話です。しかし、今回の米価の高騰や米不足は意識せずにはいられませんでした。米を食べられないことがかなりのストレスになっていて、何というか、自分はやっぱり日本人なんだなあと思ったものです。
ちなみにネットで「令和の米騒動」と検索するとたいてい他に2つの事件がヒットします。1つは「中日ドラゴンズによる令和の米騒動」で、簡単にいうと同球団の選手が試合前の食事で米を食べられなくなったというものです。もう1つが2020年にゲームソフト『天穂のサクナヒメ』のパッケージ版が品薄となった状況を指すものです。なぜゲームの品薄が「米騒動」と形容されたのかというと、このゲームは豊穣の女神を主人公とした稲作を題材としたアクションRPGだからです。私もやってみたのですが、よくあるRPGと違って敵を倒してレベルアップをするのではなく、稲を育てて収穫することで強くなっていくという変わった強化の仕方をします。稲作の行程はかなり本格的で、ほとんど楽ができないのですが、試行錯誤の末、育てた稲が見事に実った感動はひとしおでした。私もゲームのストーリーを進めるよりも稲作にはまってしまった結果、序盤にもかかわらずゲーム内の時間で10年くらい稲作に没頭してしまいました。
ところで、稲にも花言葉があります。「神聖」です。これは日本の神話において稲作が重要な位置づけをされているためで、神道の儀式では稲穂や米が重要なアイテムとして用いられることも多いです。また米一粒には7柱の神が宿っているといわれています。つまり、お米を食べることは神さまの恩恵をいただくことでもあり、だからこそ一粒一粒を大切にいただかなければならないという教えが古くからあるわけです。令和の米騒動をきっかけに改めて感じたお米の大切さはずっと忘れないでいようと思います。