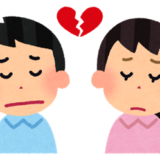国語を教えていて、漢字の書き取りなどの際に、せっかく国語辞典を引いているのに、意味を考えずに書くものだから全然よくわからない熟語を答えてしまう人が少なからずいます。
漢字には意味があるので、おなじ読み方でも意味を考えて書くんだよ、と教えると、その場ではできるのですけれど、次の週にはまた同じような間違いをしてしまうのですね。もちろんそこを教えて理解してもらうのが仕事なわけですけれども、そもそもなぜ「文字には意味がある」ということが身につかないのでしょう?辞書を引く習慣とかがついていないからでしょうか?とりあえず辞書と言えばで思い出すのはこの『舟を編む』です。
https://books.kobunsha.com/book/b10127143.html
現在、言葉の意味が分からないときにとりあえず辞書を引くという人はまずいません。スマホで検索してしまいますよね。それだって駄目じゃないんです。わからない言葉をわからにままにしてしまう人の方がもっと多いわけで調べるだけでもえらい。
でもやっぱり辞書を引いてほしいなあと、複数ある意味を見て、その言葉を使った例文とかを読んで、できれば周りの見出しにも目を通して、こんな言葉もあるんだあ、とか思ってみたりして、なんならページをめくってる最中に面白そうな言葉を見つけて寄り道したっていいわけで、検索して調べるのでもまた違った学びはあるんでしょうけども、どうにも古い感覚が抜けません。
だから辞書は辞書でも電子辞書もあまり好きじゃないんですよね。便利は便利なんでしょうけども。なんか最近は答えさえ分かればいいとかいう子が多い気がします。コスパとかタイパもいいんですけど、こと勉強するとなったら遠回りの部分も全部学びになるわけで、そうなると「便利な」スマホとか電子辞書でなくても、「不便な」紙の辞書にもいいt頃が多いと思うんです。
そういえば知り合いに辞書を読むのが趣味、という人がいました。本当に1ページ目から順番に読んでいくんだそうで、そこまでいかなくても、暇なときにペラペラめくってみるくらいして、辞書とお友達になりましょうよ。世界が広がりますよ。嘘じゃないよ。